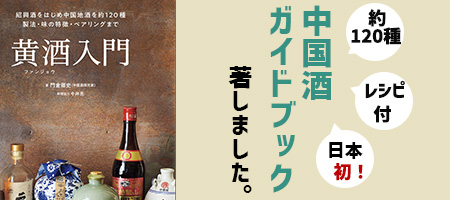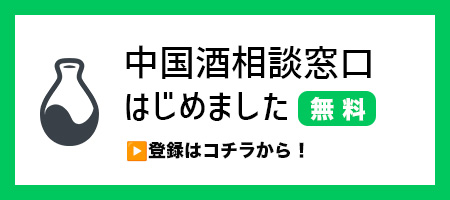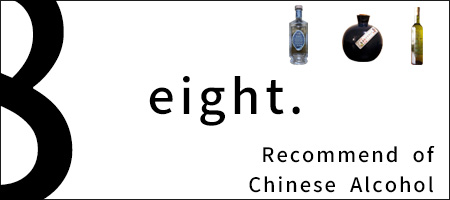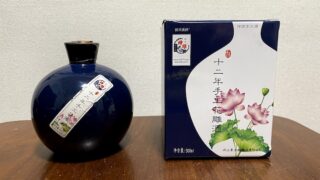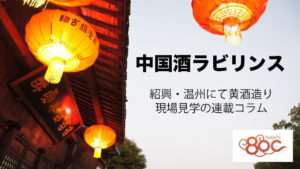干杯!中国酒探究家のdonです。
さて、日本酒と紹興酒はアジアを代表する米の醸造酒です。
この2種の酒はさまざまな共通点がありながら、色や風味は全くといっていいほど異なります。
そこで今回は紹興酒と日本酒の違いについてまとめてみました。
ご興味のある方の参考になれば嬉しいです。
執筆者紹介 don(門倉郷史)
 日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。赤坂・六本木・銀座にある中国郷土料理店で約9年勤務し、黄酒専門店責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。
日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。赤坂・六本木・銀座にある中国郷土料理店で約9年勤務し、黄酒専門店責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。
- 中華料理店のホール担当
- 紹興酒(黄酒)や白酒など中国酒輸入会社の方々
- 中国酒について知りたいソムリエ・唎酒師の方など
「紹興酒について基礎的なことから知りたい!」という方はこちらの記事をご参考ください!

日本酒と紹興酒の共通点を確認!

日本酒と紹興酒はにはいくつもの共通点があります。
例えば以下の通りです。
- 製造工程が似ている
- 原料が米の醸造酒
- 麹が必要
- 並行複発酵
・・・etc
日本酒と紹興酒は大まかな点で見れば製造工程が似ています。そしてそれぞれ共に米を主原料とした醸造酒です。
酒を造るためには麹が必要で、容器の中で糖化・アルコール発酵を同時に行っていくという高度な発酵技術「並行複発酵(へいこうふくはっこう)」によって造られます。
このように共通点が多いのに、なぜあれほどまでに色や風味が異なるのでしょうか?
それは、細かく見ていくとさまざまな点で違いがあるからです。
では具体的に両者の違いを見ていきましょう。
日本酒と紹興酒の違い6選
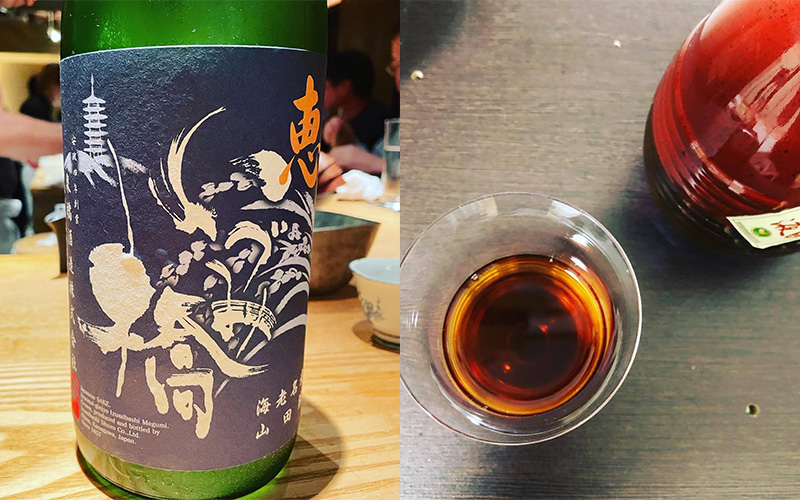
日本酒と紹興酒におけるそれぞれの違いは、以下6つの側面で見てとることができます。
- 原料
- 精米歩合
- 片白と諸白
- 菌の種類
- 発酵・貯蔵に用いる容器
- 酸の構成成分
それぞれ解説します。
※まだありそうなので、新しい情報を発見次第、追加していきます。
原料
「さっき、原料は同じ米だって言ってたじゃないか!」
そんな声が聞こえてきます(笑)
両者とも米を使用した醸造酒には違いありませんが、米といっても、うるち米と糯米、インディカ米などさまざまな種類があります。
その中で、日本酒はうるち米を使用し、紹興酒は糯米を使います。
なぜ紹興酒は糯米を使用するのか?これはまだ調査が必要ですが、中国酒について書かれた書籍「黄土に生まれた酒」によるとこのような表記があります。
「漿水(しょうすい)で仕込む製法はかつて日本酒にもあった。発酵が不十分な清酒となってしまうことが多く廃れてしまった。紹興酒では日本酒のように原料米の粳米澱粉が老化して糖化されなくなるのとは違って糯米澱粉は老化せず容易に溶ける。」
引用:「黄土に生まれた酒」花井士郎著※一部省略しながら抜粋
中国では浸漬の際に乳酸発酵させた水を漿水といいます。紹興酒はこれを仕込みの水に使用します。
以上の文章は、糯米は漿水を使用しても老化せずに溶けるため、この製法に適しているということが語られています。
ただ、これが糯米を使用する理由とするのは、少し無理があるかなと思います。
なぜなら、日本酒でも乳酸発酵した水「そやし水」を使用する「菩提酛(ぼだいもと)」という同様の製法があり、現代で復活しているからです。
以上のことから、糯米を用いるのにはさらに別の理由が考えられるんじゃないかと思います。かつて紹興酒もうるち米で作られていた時代があるとも言われています。この点はわかり次第追記していきます。
- 日本酒はうるち米の醸造酒
- 紹興酒はもち米の醸造酒
精米歩合
日本酒の精米歩合は基本的に70%前後と言われていますが、紹興酒は90%程度とあまり削りません。これは、日本の食用米と同じぐらいの割合です。
米の表面にはタンパク質や澱粉などが含まれています。タンパク質はアミノ酸の源で、旨味の源であるのと同時に苦味や雑味も生むため、日本酒は米をしっかり削ります。
紹興酒はアミノ酸が豊富で日本酒の数倍と言われています。その理由は、この糯米をあまり削らないことがひとつ考えられます。
なぜあまり削らないのか?
理由は定かではありませんが、個人的には次のように考えます。
紹興酒はなぜそれほど米を削らないのか?
紹興酒が米を削らない理由は、以下の二つが考えられます。
- 大きな米で酒造りをすれば多くの酒を造ることができる
- 精米機があまり普及していない
米を削らなければ、その分大きな状態で酒造りに使用することができます。
中国は、食材の使用法を見てもなるべく効率的に全ての部位を使用するような工夫をします。これは酒造りでも同じなのではないか、というのが僕の考えです。
例えば、白酒を造るときに出た酒粕は豚の肥料に用いられます。このサイクルは発酵界の巨匠である小泉武夫先生が発見し、世界的に注目を浴びました。
紹興酒においても、米を削らずに大きい状態で使用して少しでも多くの酒を造るという考えに至るのは自然なことなのかなと思います。
もう一つは、精米機自体がそれほど多く流通していないことが考えられます。
これはデータがあるわけではありませんが、僕自身、黄酒の情報を収集する中で日本酒のような高精白できる精米機の存在をあまり耳にしたことがありません。
なので、そもそもそういった環境が整っていないのかな、と推測します。
あくまで個人的な考えなので、参考程度に見ていただけたらと思います。
- 日本酒の精米歩合は約70%以下だが、紹興酒は約90%とあまり削らない
片白と諸白
「片白(かたはく)」「諸白(もろはく)」という言葉をご存知でしょうか。
掛米と麹米の両方とも精米して造られた酒を「諸白」、掛米だけ精米して麹は玄米を使用するものを「片白」といいます。
今は日本酒のほとんどが諸白にあたりますが、江戸時代以前のまだ精米の技術がなかった時代では、片白が主流でした。
紹興酒は、今でも片白で造られます。しかも、掛米は糯米、麹米は玄麦とそれぞれ異なる原料を使用するのもひとつの特徴でしょう。
- 諸白(精米:掛米○ 麹米○)→日本酒
- 片白(精米:掛米○ 麹米×)→紹興酒
「諸白」
http://www.nada-ken.com/main/jp/index_mo/557.html
引用:「諸白」灘酒研究会HPより
菌の種類
日本酒と紹興酒では使用する麹の種類が異なります。日本酒は米麹、紹興酒は麦麹(曲)を使用します。これらの麹に繁殖する菌は種類が異なります。
- 米麹:黄麹菌
- 麦麹(曲):クモノスカビ、毛カビ
※紹興酒では麹を「曲(きょく)」といいます。
黄麹菌を使用した発酵文化は日本特有のもので、他のアジアの国ではクモノスカビなどが繁殖した麹を酒造りに使用するケースが多く見られます。
・・・と今まではこの説が当たり前のように語られていましたが、最近この常識が覆されつつあります。
なんと紹興酒の麦曲にも黄麹菌が多数存在していると言われるようになってきています。
元々、麦曲にも黄麹菌は存在していたのです。なぜクモノスカビがフューチャーされたのか?それは紹興酒の個性を打ち出すためではないか、と個人的には思っています。
間違いなく言えることは、麦曲には黄麹菌だけでなくクモノスカビや毛カビなどさまざまな菌が繁殖しているということ。クモノスカビは、フマル酸など独特な酸味を生成すると言われています。
紹興酒の複雑味は、さまざまな菌の活動によって生まれているといっても過言ではありません。
- 日本酒は米麹を使用し、主に黄麹菌が繁殖している
- 紹興酒は麦曲を使用し、主に黄麹菌やクモノスカビなど多数の菌が繁殖している
発酵・貯蔵に用いる容器
米の醸造酒は原料を発酵させたり貯蔵するために、大きな容器が必要です。
日本酒は一般的にタンクで発酵・貯蔵を行いますが、紹興酒は甕を使用します。
タンクは完全密封で空気を遮断しますが、甕には通気性があり、若干空気(酸素)が入り込むことで良好な発酵を促すことができます。
紹興酒は野外で甕を保存するため、温度調節が非常に困難ですが甕を利用することで気化熱の作用が発生するため、自然の中で発酵するには甕の方が適しているといえるでしょう。
しかし、これは伝統的な製法における話で、近年では紹興酒の製法も大手を中心に工業化され、タンクを使用するところも増えてきています。今後この動きはより進んでいくのではないかと思われます。
常連さんから面白い話を聞いた。トルコで水の運搬を空気穴のある素焼き甕で行う。これは気化熱によって水の温度が上がらないため敢えて使っているらしい。紹興酒が甕で発酵させるのも一緒?温度調節は発酵にとって重要なので同じような効果を狙っているのかもしれないhttps://t.co/WI6T4Zzu5j
— don (@umaddon1) January 7, 2022
- 日本酒の発酵や貯蔵は主にタンクを使用する
- 紹興酒の発酵や貯蔵は主に甕を使用する
酸の構成成分
日本酒と紹興酒の大きな違いのひとつ、「酸」の構成成分です。これは風味の違いに大きく影響していると言ってよいでしょう。
紹興酒の酸は主に乳酸(50%以上)、フマル酸、酢酸です。対して日本酒はコハク酸、リンゴ酸、乳酸、クエン酸です(参考:「黄土に生まれた酒」花井四郎著)。近年ではリンゴのようなフルーティさの感じられるカプロン酸エチルやバナナ臭の強い酢酸イソアミルなどが多く含まれる日本酒が増えています。
仕込み水に漿水を使用する紹興酒は、乳酸量が格段に多くなります。さらに紹興酒はアミノ酸が豊富なため、味全体がくどくなりやすいのですが、この乳酸の存在が味全体をシャープにする役割も果たしています。
- 日本酒の酸は主にコハク酸、リンゴ酸、乳酸、クエン酸、カプロン酸エチルや酢酸イソアミルなど
- 紹興酒の酸は主に乳酸(50%以上)、フマル酸、酢酸
まとめ
今回は、日本酒と紹興酒の共通点、そして違いをまとめました。
最後に、それぞれの6つの違いについてまとめます。
| 原料 |
|
|---|---|
| 精米歩合 |
|
| 片白と諸白 |
|
| 菌の種類 |
|
| 発酵・貯蔵に用いる容器 |
|
| 酸の構成成分 |
|
今、紹興酒引いては黄酒は大きな転換期にあります。その中で、日本酒文化との交流はより多く発生していき、転換のスピードもより加速していくことでしょう。
もしかしたらこれらの違いは、どんどん無くなっていく?それとも違いがより明確についていく?それはわかりません。
どちらにせよ、同じ米の酒として、それぞれ面白いお酒が生まれていくといいですね!