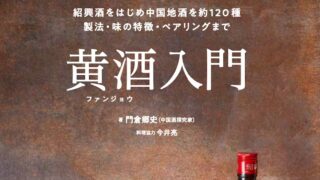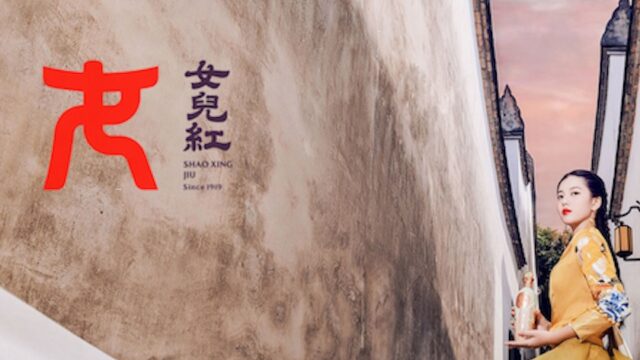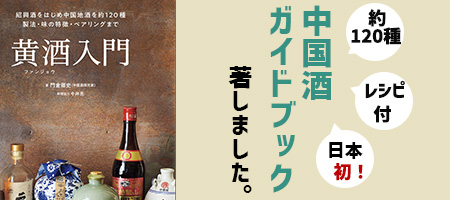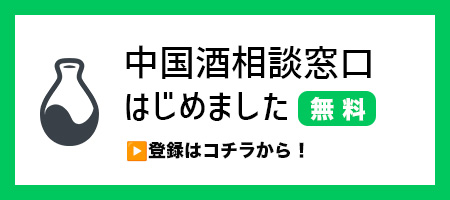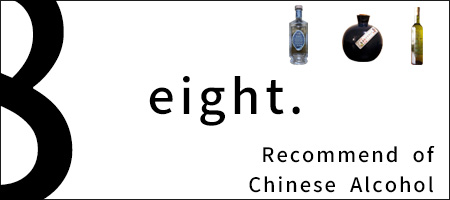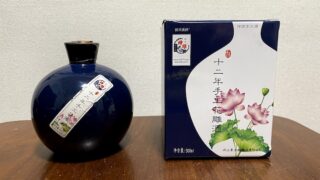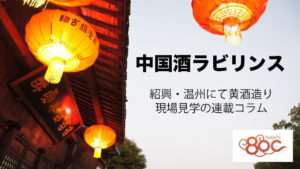干杯!
中国酒探究家のdonです。
今回は、「黄酒(ファンジョウ)」がどんなお酒なのかをわかりやすくまとめます。
「黄酒ってなに?」
「聞いたことがない。」
「紹興酒とは違うの?」
黄酒は長い歴史を持っているにも関わらず、あまり認知されていないお酒です。
広大な中国において、さまざまな地域で造られている醸造酒の一種です。
この記事では、黄酒の基礎知識や、各地域の特徴・代表銘柄などを解説していきます。
読んでいただけたら、黄酒がどのようなお酒なのか、全体的な知識や紹興酒との違いがよくご理解いただけると思います。
楽しみ方も紹介していますのでぜひ最後までご参考ください!
▼紹興酒についてはこちらで詳しくまとめております!

執筆者紹介 don(門倉郷史)
 日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。中国郷土料理店「黒猫夜」で約9年勤務し、黄酒専門店「酒中旨仙」責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。
日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。中国郷土料理店「黒猫夜」で約9年勤務し、黄酒専門店「酒中旨仙」責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。
Contents
5分で理解!黄酒とは?原料や製法など基礎知識を解説
黄酒(ファンジョウ)とは、もち米やキビなど穀物を主原料とした中国最古の歴史を持つ醸造酒です。
日本では「ファンジウ」「ホァンチュウ」などとも呼ばれています。
黄酒は中国各地で作られていますが基本的にその産地で親しまれていることが多く、大手でない限り他地域にあまり流通しません。
当然、日本にも一部しか入ってきていません。
そのため、黄酒というジャンルの認知度はそれほど高くないのが現状です。
しかし黄酒は、日本酒やワインと比べて勝るとも劣らない個性の豊かさがあり、食中酒としても非常に面白い酒です。
色だけ見ても、こんなにも違います。

当然、味わいや香りもそれぞれ異なります。
ひとつの酒ジャンルにおいて、なぜここまでの違いが見られるのか?
その理由のひとつは、原料にあります。
原料

黄酒の原料は産地や銘柄によってさまざまですが、主に使用されるものは以下の3つにまとめることができます。
- 穀物
- 曲(麹)
- 水
それぞれ解説します。
穀物
穀物とは食用される植物の種子全般をいい、主に米・麦・黍(きび)などさまざまな種類があります。
黄酒はこれらの穀物を麹で発酵させて作る醸造酒です。
黄酒に最もよく使われる穀物は糯米ですが、酒蔵や地域によっても異なります。実際、米に限らず黍やモロコシなどさまざまな穀物によって酒が作られています。
米で作る酒と黍で作る酒。種類が変われば風味も異なってくるのは当然のことではないでしょうか?
“原料が穀物”という枠組みの広さが、黄酒の多彩な個性を生んでいる要因のひとつといってもよいでしょう。
| 日本酒 | 米 |
|---|---|
| ワイン | ブドウ |
| ビール | 大麦 |
| 黄酒 | 穀物(米・麦・粟・黍など) |
曲(麹)
 提供:紹興国稀醸造酒有限会社(無断転載厳禁
提供:紹興国稀醸造酒有限会社(無断転載厳禁曲(きょく)とは、穀物に菌を繁殖させた糖化発酵剤です。
日本酒でいう麹と同じような役割を果たしますので、曲が無ければ黄酒を造ることはできないというほど、非常に重要な原料です。
黄酒の曲には種類があり、主に麦を原料とした「麦曲」が多く使われます。
麦曲に繁殖する主な菌は黄麹菌やクモノスカビで、フマル酸という独特な酸を生成すると言われています。
南方では紅曲が使用されたり、薬材を混ぜた薬曲を用いるなど、地域によって違った特色が見られます。
水
水は酒にとってまさに源といってもよいでしょう。
ただ、黄酒のラベルを見てみると「水」としか書いていないものが多く、詳細な情報が見当たりません。
実際には、醸造用の水として塩分量や鉄分などにおいてさまざまな規定が定められており、一定の基準を越えていなければなりません。
なお、最も有名な黄酒である紹興酒は「鉴湖(鑑湖)」という湖の水を使わなければならないという地域限定の規定もあります。
品質のよい水を使うというのは、日本酒と一緒です。黄酒も上質な水から生まれているのです。
作り方

黄酒は日本酒やマッコリなどと同じ並行複発酵で造られる醸造酒です。
作り方は産地や種類によって違いはあるため、ここでは黄酒で最も有名な紹興酒を例に挙げて紹介します。
黄酒(紹興酒)の製造工程
一般的な黄酒(紹興酒)は以下の流れで醸造します。
- 糯米の選定・精米
- 穀物を水に漬けて吸水させる
- 穀物を蒸す
- 穀物を冷ます
- 甕の中に原料を投入する
- 主発酵(一次発酵)
- 後発酵(二次発酵)
- 酒を搾る・ブレンドする
- 加熱殺菌
- 酒を甕に入れて熟成
黄酒の製法は、日本酒と大まかな流れが似ています。
大きな違いとしては黄酒は仕込みと麹の製法ルートが全く別であることが挙げられます。
日本酒の酒造りは10月頃から一斉にスタートします。精米した米を水に浸し、甑で蒸したあとは麹用、仕込み用として使用します。
一方で黄酒の場合、まずは夏頃に麹作りからスタートします。黄酒の主原料は糯米ですが、麹には米や麦を使用するというのが一般的です。
先ほども紹介した通り、中国では麹にあたる原料を「曲(きょく・チュー)」「酒薬(しゅやく)」(※それぞれ別物)といいます。
これらは夏〜秋頃に造られて、その後11月頃から酒の仕込みが始まります。
このように、酒の仕込みと麹作りが全く別ルートで行われるのは黄酒の特徴のひとつといえるでしょう。
より詳しく紹興酒の製法について知りたい方は、下記を併せてご覧ください。

歴史
黄酒の歴史は長く、4,000年とも10,000年とも言われています。
なぜこれほどまでにバラツキがあるかというと、中国ではさまざまな遺跡が発掘されており、どの遺跡による発見が酒造りの始まりとして見るかで説が変わるからです。
ここでは、これまでに中国で発見された遺跡・文化をいくつか紹介します。
1万年前 | 上山遺跡(浙江省金華市)
上山遺跡は2000年に発見された浙江省金華市浦江県で発見された遺跡群。
上山考古遺跡公園では炭化した1粒の米「万年米」が発掘され、1万年前から稲作が行われていたと見られています。
1万年前は新石器時代に当たりますが、2006年に当時の文化を「上山文化」と正式に認定されました。
銭塘江上流域と霊江流域で19ヶ所の遺跡が発見され、稲作の収穫から食用に至るまでの形跡が整った状態で残っています。
酒造りとの関連性は不明瞭ですが、稲作と酒造りは密接な繋がりがあり、この上山文化が酒造りの起源なのではないかと考える説もあります。
「約1万年前の中国上山文化は世界稲作文化の発祥に」人民網日本語版
9,000年前 | 橋頭遺跡(浙江省義烏市)
橋頭遺跡(きょうとういせき)は浙江省金華市に隣接する義鳥市で見つかり、上山文化に属します。
素焼きで絵画や模様が描かれている「彩陶(彩文土器)」が発見され、いくつかの土器の中から麹菌やクモノスカビ、酵母菌が見つかりました。約9,000年前のものと見られています。
この研究結果は米学術誌「PLOS ONE」に掲載され、イネやハトムギを主原料とした酒(ビールと見られています)が醸造されていたと発表しています。
明確に「穀物による酒造りの始まり」として発表されているのは、現時点でこの説が最古です。
「中国南部で9千年前に酒を醸造 考古学者らが論文発表」AFPBB News
7,000年前 | 河姆渡遺跡(浙江省余姚)
河姆渡遺跡(かぼといせき)は紀元前5000年〜前3000年のものと見られる集落遺跡で、浙江省余姚市にて発見されました。
稲の籾殻が大量に発掘され、稲作が行われていたと見られている一方で、古い年代ほど野生の品種も多数見つかっており、7000年前からこの地で盛んに稲作が行われていたと明言できるかは疑問という見方もあります。
ただ、年を追って栽培品種は増えており、稲作文化がこの頃に発展していったという説は強いです。
また、酒器のような陶器が多数発見されていることから、酒造りの始まりとして語られる年代でもあります。
4,000年前 | 夏王朝
夏王朝(かおうちょう)は、中国の「史記」に名を残す中国最古の伝説的な王朝。治水の神様とも言われた禹王(うおう)によって建てられ、当地エリアは山西省〜河南省周辺と言われています。
その頃に酒造りを行ったのが儀狄(ぎてき)という人物でした。紀元前1世紀に編纂された「戦国策」という遊説の書の中で、儀狄が禹王に酒を献上していたという記載がされています。
もう1人、酒造りの始祖として知られるのが杜康(とこう)です。杜康は夏王朝6代目の皇帝でもあります。日本でも有名な三国志の皇帝、曹操が「短歌行」という詩の中で杜康の名を用いています。
對酒當歌 人生幾何 譬如朝露 去日苦多
慨當以慷 幽思難忘 何以解憂 惟有杜康▼大まかな内容
酒があるなら歌おう。人生ははかないもの。でも落ち込むときもある。そんなときはどうしたらいいのか。酒を呑むしかないではないか。
杜康は日本酒の作り手である「杜氏(もりし)」の由来とも言われています。
種類
黄酒にはさまざまなタイプがあり、以下4つの種類に分類することができます。
- 干型(ガンシン) | ドライ
- 半干型(バンガンシン) | ややドライ
- 半甜型(バンティエンシン) | やや甘口
- 甜型(ティエンシン) | 甘口
これらは主に糖分含有量によって区別されています。つまり、簡単に言うと甘口なのか辛口なのかで種類が異なるということです。
なお、これらの4種類は糖分含有量だけでなく、さまざまな成分においても量が規定されています。
以下に表でまとめます。
| 糖分 | 15g未満(1リットル中) |
|---|---|
| 酸度 | 4.0-7.0g(1リットル中) |
| アルコール度数 | 13.0°〜20° |
| アミノ酸 | 0.5g以上(1リットル中) |
| 糖分 | 15.1〜40.0g未満(1リットル中) |
|---|---|
| 酸度 | 4.5-7.5g(1リットル中) |
| アルコール度数 | 14.0°〜20.0° |
| アミノ酸 | 0.6g以上(1リットル中) |
| 糖分 | 40.1〜100.0g未満(1リットル中) |
|---|---|
| 酸度 | 5.0-8.0g(1リットル中) |
| アルコール度数 | 12.0°〜20.0° |
| アミノ酸 | 0.5g以上(1リットル中) |
| 糖分 | 100.0g以上(1リットル中) |
|---|---|
| 酸度 | 4.0-8.0g(1リットル中) |
| アルコール度数 | 15.0°以上 |
| アミノ酸 | 0.4g以上(1リットル中) |
ちなみに、日本で流通している黄酒は90%以上が紹興酒(半干型)です。
以下、紹興酒を例にしながら黄酒の種類について詳しく解説しております。ご興味のある方はご参考ください!

アルコール度数
黄酒のアルコール度数は、12〜20度程度が一般的です。近年では低度の黄酒も製造されており、8〜9度のものもあります。
「中国酒って度数高いよね!」と言われることがありますが、他の醸造酒と比べると日本酒と同程度であることがわかります。
| 日本酒 | 15°〜16° |
|---|---|
| ワイン | 12°前後 |
| ビール | 4〜7° |
| マッコリ | 6〜8° |
| 紹興酒 | 14〜16° |
中国酒=度数が高い、というイメージは恐らく、50度以上ものアルコール度数を誇る白酒のイメージが強いのかもしれません。
より詳しく黄酒のアルコール度数について知りたい方は、こちらで紹興酒を例にしながら詳しく解説しています。よかったらご参考ください!

味わい
黄酒は甜味や酸味など6つの味のバランスが重要とされています。
この黄酒を構成する6つの味を「六味」といいます。
六味は、下記の6つです。
- 甜味(あまみ)
- 酸味(さんみ)
- 苦味(にがみ)
- 辣味(からみ)
- 鮮味(うまみ)
- 渋味(しぶみ)
この六味を意識しながら味を見ることで、各黄酒の個性を掴み取ることができるようになります。
六味についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

紹興酒と黄酒の違い
「黄酒?そもそも聞いたことがない」
「中国酒は、紹興酒のことでしょ?」
「明確な違いがよくわからない・・・」
そんな素朴な疑問を持つ方も少なくないと思います。
日本において中国酒といえば紹興酒であり、黄酒との違いが理解しづらいのも当然です。
黄酒と紹興酒の違いは、他のお酒を例にすると理解しやすくなります。
以下、テキーラとシャンパンと紹興酒を一覧にしてまとめました。
| テキーラ | メスカルという蒸留酒の一種。テキーラ地方で作られており、ハリスコ州の政府が定めた規則に則って作られた一級品のメスカル |
|---|---|
| シャンパン | シャンパーニュ地方で醸造され、フランスが定めた基準を全てクリアした一級品のスパークリングワイン |
| 紹興酒 | 浙江省紹興市で醸造され、国家や紹興市が定めた基準をクリアした一級品の黄酒 |
要するにこれらのお酒は、国家が品質を担保するために規定した基準をクリアした「地理的表示」に準じたお酒です。
紹興酒は黄酒の一種であり、紹興という酒造りに最適な地で作られたお酒だと国が認めていることを示しています。
日本においては黄酒よりも紹興酒の認知度が高いため、混乱を招きやすい要因となっています。
より深く黄酒がわかる3つのトリビア
黄酒がどのようなお酒なのか、だんだんと掴めてきたのではないでしょうか。
より深く黄酒について知っていただくために、普段よく聞かれる以下3つの疑問について解説したいと思います。
- 米の酒なのに、なぜ琥珀色なのか?
- なぜ”黄酒”なのか?
- 歴史は古いのになぜ知られていないのか?
米の酒なのに、なぜ琥珀色なのか?
黄酒は、多くが透明感のある琥珀色をしています。
しかし、同じ米の酒である日本酒は基本的に透明です。なぜ黄酒は琥珀色になるのでしょうか?
答えは下記の3点です。
- アミノ酸の量
- 麹に使用する小麦の色
- カラメルの添加
それぞれ解説します。
琥珀色の理由①アミノ酸の量
黄酒はアミノ酸の量が多く含まれています。そのため、甕の中で糖分と結合してメイラード反応が活発化し、着色していくのです。
日本酒にもアミノ酸は含まれていますが、黄酒の方が量は多く熟成期間も長いため、メイラード反応が起きやすいといえます。
琥珀色の理由②麹に使用する小麦の色
麹の原料となる小麦は皮ごと使用するため、その色も酒色に大きく影響します。
日本酒は諸白(もろはく)といって、麹用の米と仕込みで用いる米の両方を精米します。
しかし黄酒は基本的に麹米は精白しません。(これを片白(かたはく)といいます。)
これも日本酒と黄酒の大きな違いのひとつです。
琥珀色の理由③カラメルの添加
黄酒は紹興酒を中心にカラメルを添加します。
カラメルは味には影響しない程度の量で、着色と光沢のために使用されます。
ただ、近年はカラメルを添加しないノンカラメルタイプも増えてきており、熟成のみでも綺麗な琥珀色になることがわかってきています。
以上、3点が黄酒が琥珀色となる理由です。
なぜ”黄酒”なのか?
黄酒という名称が初めて世の中に出たのは、14世紀後半〜17世紀中盤に栄えた明の時代。
当時編纂された「天工開物」という中国で伝統的に継承されている産業技術の解説書の中で、初めて黄酒という名称が登場しました。
「黄」は琥珀色を意味し、まさにその酒色を示しています。
歴史は古いのになぜ知られていないのか?
なぜこれほどまでに黄酒の認知度が低いのでしょうか。
「黄酒と紹興酒の違い」の部分でも少し触れましたが、それは紹興酒の存在感が大きいからです。
紹興酒以外の黄酒は地元で愛されるものが多く、あまり他地方に流通していないのが現状です。
実際に紹興酒はアメリカやヨーロッパのチャイナタウンにも流通しておりますが、他地域の黄酒はほとんど見られません。
そのため、世間一般的には中国の醸造酒=紹興酒という認識が出来上がっているといえます。
実際日本でもテキーラをきっかけにメスカルの認知度は高まり、メスカルを豊富に置くレストランも存在します。
黄酒の特徴を4つの地域に分類して解説

黄酒は特徴によって大きく4つのエリアに分類することができます。
北方黄酒(ほっぽう)
山東省や陝西省など中国北部エリアの一部で、黄酒が造られています。
北方黄酒の特徴は個性的な黄酒が多いということ。その理由は、黍米(キビ)や黒米を使用するなど主原料がさまざま異なるためです。
北方黄酒の特徴
- 産地:山東省、内蒙古、陝西省など
- 原料:黍や黒米などさまざま
- 味わい:独特で紹興酒とは一線を画す
- 代表銘柄:即墨老酒(ジーモウラオジョウ)
代表銘柄である即墨老酒とは、黍を大鍋でドロドロになるまで炒め煮込み、その焙煎の香りがお酒の味わいとしてダイレクトに表れる唯一無二な黄酒。

(2024/07/27 06:22:27時点 楽天市場調べ-詳細)
江南黄酒(こうなん)
浙江省や上海周辺エリアは最も黄酒が造られている名産地域です。
代表的な黄酒「紹興酒」と同様に、糯米を麦曲で醸していく製法が主流です。
江南派黄酒の特徴
- 産地:浙江省、上海、江蘇省など
- 原料:糯米・麦曲が主流
- 味わい:紹興酒系の風味が多い
- 代表銘柄:古越龍山、石庫門
紹興酒最大手の古越龍山(こえつりゅうざん)は、日本でも数多く流通している業界のリーディングカンパニー。
もう一つ挙げた「石庫門(シークーメン)」は、上海で唯一の黄酒メーカー「上海金枫酒股份有限公司」の代表ブランド。紹興酒のような味わいもありながら、軽やかで紅茶のようなフローラル感が個性を感じさせてくれます。
南方黄酒(なんぽう)
福建省や広東など、中国沿岸部南方にも盛んに黄酒を製造しているエリアがあります。
福建省の「沉缸酒(チェンガンジョウ)」は、全国評酒会で3度金賞を受賞し、「黄酒之冠」と評された実績ナンバーワンの黄酒です。
南方の黄酒は糯米を使用しながら紅曲を中心としてさまざまな麹を使用するのが特徴。温暖な気候の中、腐敗を防ぐために糖度を高める傾向があり、甘口タイプの黄酒が多く存在しています。
南方派黄酒の特徴
- 産地:福建省、広東省など
- 原料:糯米・麦曲が主流
- 味わい:濃醇で甘口タイプが多い
- 代表銘柄:沉缸酒
沉缸酒(チェンガン)は、紅曲と、漢方をいくつも混ぜ合わせて作られた「薬曲」を使用し、まろやかで優しい甘味と、鼻を抜けていく独特な後味が特徴。
西方・華中黄酒(せいほう・かちゅう)
黄酒は浙江省や上海を中心に、沿岸部で醸造されていると言われていました。
しかし、実際には四川省や湖北省など中国の中心部や西部でも黄酒が醸造されていることがわかりました。
最も広いエリアであり、情報が最も少ないエリアでもあります。
最後に各地方ごとにおすすめの黄酒を紹介していますので、ぜひご参考ください!
黄酒を楽しむためのおすすめな飲み方
黄酒はさまざまな飲み方で楽しむことができます。
ここでは黄酒の飲み方を紹介します。
黄酒の基本的な6つの飲み方を紹介
さて、黄酒はさまざまな飲み方があります。下記、一覧にしてまとめました。
| ①常温 | 最もオーソドックスな飲み方。黄酒本来の味が楽しめる。まずはここから! |
|---|---|
| ②燗 | 湯煎やレンジなど温めて飲む方法です。酸味が強い黄酒は、温めすぎると余計に酸が際立つので要注意! |
| ③冷酒 | 冷蔵庫でボトルごと冷やすと、渋味や酸味がシャープになって飲みやすくなります。 |
| ④ロック | 氷を入れると、飲み口は柔らかくなりますが、味が薄まってしまうのでその点だけ気をつけたいところ。 |
| ⑤加える(干し梅や生姜など) | 紹興酒だと干し梅を入れたり、レモンスライスを入れる飲み方もあります。 |
| ⑥割る | 炭酸水やジンジャエール、コーラなど割るドリンクによってさまざまな味わいが楽しめます。 |
そのためにも、まずは常温で味を確かめること。素の味がわからなければどのようにアレンジすればよいかも見えません。
以下の記事では紹興酒の飲み方について、詳しくまとめています。ご興味のある方はご参考ください!

黄酒が楽しめる場所3選
黄酒を楽しめる場所は、以下の3つが考えられます。
- 中華料理店・レストラン
- 自宅
- 現地中国
それぞれ解説します。
中華料理店・レストラン
黄酒はまだ家飲み文化がそれほど根付いておらず、レストランなど飲食店の方が楽しみやすいのが現状です。
お店なら、町中華よりも中華レストランがおすすめです。
町中華は紹興酒が1〜2種ある程度で、さまざまな黄酒が楽しめる店舗はほぼありません。
中華レストランもまだ数は多くありませんが、都心を中心に黄酒が楽しめるお店が増えています。
中には、料理とのペアリングやワイングラスで提供している店舗もあるため、しっかりと楽しむことができます。
以下のページには東京で黄酒が楽しめるレストランをまとめているので、ご興味のある方はご活用ください。

自宅
黄酒を自分で購入して、自宅や友人宅などで楽しむこともできます。
黄酒はインターネットや店舗で購入できます。ただ、種類はそれほど多くなく、ほとんどが紹興酒です。
紹興酒の購入場所として一番手軽でおすすめなのは、Amazonや楽天などインターネット通販サイトです。
スーパーやコンビニでは、紹興酒をほとんど置いていません。
あっても1種。2種以上あれば「品揃えがいいな」と感じるぐらいです。
上野や新大久保にある大型の中華食材店は種類も豊富!
- 新大久保や上野にあるような中華食材店
- インターネット
- 酒販店
- スーパー・コンビニ
▼YouTubeで紹興酒が購入できるおすすめの場所を紹介しています!
現地中国
産地である中国に行けば、当然飲むことができます。
日本に流通している黄酒はほんの一部で、中国には未知なる銘柄がたくさんあります。
ただ、やはり有名なのは紹興酒で、他地方の黄酒は地元で親しまれているものがほとんどです。
予め気になる銘柄を調べて、直接その場所に行くのがよいでしょう。
紹興なら、「黄酒博物館」や「魯迅故居」などの観光地で紹興酒の試飲が可能です。
黄酒にぴったり!おすすめのおつまみ・料理
自宅や友人宅でのホームパーティなど、自分たちで黄酒を楽しみたいときに大切なのが、おつまみ。
黄酒はしっかりとしたボディ感があり、中華料理に限らず、発酵やスパイス料理など幅広い料理と楽しむことができます。
実際にどのような料理と合うのか、一覧にまとめてみました。
黄酒に合うおつまみ・料理一覧
| 肉料理全般 | 羊肉や鴨肉などの肉料理は黄酒との相性が良いです。唐揚げなどの揚げ物やステーキなど焼き物などさまざま調理方法の肉料理と楽しむことができるでしょう。 |
|---|---|
| 発酵食品・料理 | チーズや腐乳(中国の発酵豆腐)などの発酵食品も、黄酒のおつまみにピッタリです。 |
| スパイス料理 | 黄酒の多彩な要素が感じられる風味は。香辛料の味や香りと渡り合います。他のお酒にはないマリアージュが生まれることでしょう。 |
| 和食 | 黄酒の中には優しい味わいのものもあり、和食との相性も楽しめます。特に出汁がしっかりと感じられる肉じゃがやおでんなどがおすすめです。 |
| 定番!中華料理 | 麻婆豆腐、餃子、回鍋肉など日本でお馴染みの中華料理と楽しむのは定番中の定番!シュワっとしたくなったときは、炭酸で割ってハイボールにするのもおすすめです。 |
この投稿をInstagramで見る
黄酒入門におすすめな銘柄3選
さて最後に、初めての黄酒におすすめな銘柄を3つ選びました。ご参考になれば幸いです。
北方黄酒 | 黒米(ヘイミー)

中国北方にある黄酒名産地「陝西省洋県」。国家が保護する自然特区で育まれた一級品の黒米を使用した軽やかな風味が特徴の黄酒です。
- 原料:黒米,麦曲
- 度数:12度
- 型:半干型
- 産地:陝西省洋県
江南黄酒 | 東湖12年(ドンフー)

東湖は紹興市にある湖の名称で、その名を冠した紹興酒です。
東湖は、他の紹興酒とは明らかに異なる風味を持っています。ふわっと香るの果実香。爽やかで熟したような柑橘系。飲んでも軽やかで酸・甘・旨のバランスが絶妙!
- 原料:糯米,麦曲
- 度数:14度
- 型:半干型
- 産地:浙江省紹興市
(2024/07/27 11:44:59時点 楽天市場調べ-詳細)
南方黄酒 | 缸缸好(ガンガンハオ)

沉缸酒(チェンガンジョウ)の現代版タイプ。すっきりと飲みやすく改良されており、日本人にも親しみやすい丸みのある味わいです。
- 原料:糯米,紅曲,薬曲
- 度数:14度
- 型:半甜型
- 産地:福建省龍岩
まとめ
黄酒がどのようなお酒なのか、おわかりいただけたでしょうか?
黄酒は輸入している会社が1社しかなく、日本に流通している銘柄はかなり限られます。
飲み方や楽しみ方、ペアリングなどまだまだ未開拓の分野なのでポテンシャルがあり、今後が楽しみなお酒といえます。
疑問点や「こんな黄酒見つけました!」などあればいつでも気軽にご連絡ください!
▼黄酒入門の詳細